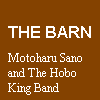 マス・システムをビートしろ
マス・システムをビートしろ
僕がHPやメールで書いたことの真意をここでもう少し説明しておきたいと思います。「このアルバムの音、具体的に言えばこのウッドストック仕様が、現代のマス・リスナー、例えばロックン・ロールの最も切実なリスナーであるべきティーンエイジャーたちにどうコミットしようとしているのか」と僕は前回のメールで書きました。これと同じことはHPにも、それからフォーラムにも書きました。これはもちろん佐野に「昔のようなジャンプできるロックン・ロール」をやれと言っているのでもなければ、タイ・アップを取ったりキャンペーンを打ったりして商業的な成功を追求せよと言っているのでもありません。
この背景には僕のベーシックなロック観があります。僕はロックは基本的にティーンエイジ・ミュージックであり、本質的にジャンクであると思っています。誰でも十代の頃に感じるであろう理屈で説明できないような怒り、苛立ち、不安や不満、あるいは逆に言葉にならない高揚した気持ち、そうしたものを理屈を経由することなしに解放するのがロックの本来の役割であり、ロックは本来的にオーバーグラウンドのメイン・カルチャーにはなり得ない、なってはならない存在だというのが僕の持論です(かつて手塚治虫が「マンガを文化だなんて呼んではいけない」と言っていたのを思い出します)。それはロックが我々の宝でありヤツらの宝ではないということなのです。これを前提にすれば、ロックは、そうした「ロック・エリートでない」、もやもやを抱えて日々右往左往している普通のティーンエイジャーのために鳴らされるべきであり、僕たちのようなリスナーは本来そのようなロックの一次的なリスナーの感じ方に対して謙虚であるべきだと思っています。
かつて僕たちがそのティーンエイジャーとして「アンジェリーナ」なり「ガラスのジェネレーション」なり「SOMEDAY」を聴いたとき(僕の場合は「Sugartime」だった)、それらはまさにそうした僕たちの寄る辺のなさとか無軌道さとかに本当にビビッドに呼応していました。それらはまるで「僕たちのこと」を歌っているように思えました。だからこそ僕たちはまるでそこに何かの救いを見出そうとするかのように佐野を聴き続けて来たのです。しかし、この「THE BARN」が果たして現代のティーンエイジャー、あるいは現代の「クソガキども」に、そのような意味あいでビビッドに届くでしょうか。この音が、「クソガキども」の今夜のもやもやを救い、彼らが成長するための宝になり得るでしょうか。
もちろん佐野も僕たちも年をとります。いつまでも「クソガキども」のために音楽を作り続けることはできないのかもしれません。しかし「クソガキども」の率直な共感を得られない音楽はもはや「ロック」ではないと僕は思います。その意味で、このアルバムがどこに向かうべきものなのかを考えたい、考えて欲しいという気持ちをこめて問題を提起しているのです。かつて佐野元春に何回も助けてもらった一人の「クソガキ」として、そしてジャンクをこそ愛する32歳のロック・ファンとしてね。
マス・システムをビートするなんて言うと確かにちょっとニュアンスが違ってしまうかもしれないけども、僕が問題にしたかったのはそういうことなのです。
(ある人にあてたメールより、一部加筆・修正)