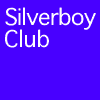 THE SONGWRITERS 2nd Season Vol.5 / Vol.6 鈴木慶一 THE SONGWRITERS 2nd Season Vol.5 / Vol.6 鈴木慶一セカンド・シーズンで唯一、佐野より年上のゲストとなったムーンライダースの鈴木慶一。キャリアが長く独自のポジションを確立しているアーティストだが、どちらかといえばミュージシャンという印象の強い人だったので、この番組への登場は意外だった。 例によって僕はムーンライダースの音楽はあまり知らない。ずっと昔にアルバムを1枚だけ持っていたはずだが、CDの時代になってからは聴く機会もなく、新譜もフォローしてないので、番組で紹介された曲も初めて聴くものばかりだった。 僕のイメージでは、鈴木慶一は小西康陽に近い。彼らは自分の内側からどうしようもなく音楽がわき上がってくる芸術家、音楽家というよりは、さまざまな音楽をお手本として自分の中に取り込み、それを消化し、攪拌し、アレンジして、最も文脈に合ったものとして提示する一種の職人のような人たちであり、彼らのクリエイティビティはそういう形で発揮されているのだと思う。 それは鈴木が学生からの質問に答え、映画音楽などの制限の多い仕事の方がやりやすいと発言していたことからも窺える。鈴木にとって音楽は生業であり、音楽を生み出すプロセスは極めて自覚的で意識的なものなのではないだろうか。その意味で、鈴木は非常にインテリジェントなアーティストであると言える。 それは詩作においてもあてはまるように思える。自分の内側からイメージがあふれ出し、それを言葉に写し取るのではなく、自分の中に営々と蓄積された語彙、イメージのライブラリーの中から、その場に最も似つかわしいものを拾い上げてくるのではないか。 鈴木の作品がロック表現として高い価値を認められているのは、そうした音楽や語彙、イメージの蓄積が極めて良質なものだからである。その蓄積の実体は彼が思春期から聴き続けたであろう膨大な量の洋楽であり、番組でも発言していたように愛してやまない映画であろう。そしてそれを整理し統合する明晰さもまた必要だ。この日の番組での語り口からも、鈴木が極めて正統的な教養人であることが窺われる。 そしてまた、そこから作品として的確なものをすくい取るセンスも重要である。鈴木が「湿気を取り除いて乾きたかった」と発言しているとおり、日本的な情緒に寄りかからず、洋楽の「カッコよさ」を日本語で表現したいというモチーフが、日本のポピュラー・ミュージックのメイン・ストリームがいまだにそうした「湿気」から自由になれない中で、そして鈴木自身「仕事」として一方でそうした音楽ともかかわりながら、自らの名義の作品では非常に独特の表現で安易な共同性に依存しない音楽を構築している原動力なのではないかと思った。 だが、番組の趣旨に即して言えば、そうした教養人としての鈴木の中のどこから、あの独特の文学性を秘めた、シニカルな歌詞が立ち上がってくるのかという探求は不発に終わったように思える。鈴木自身は佐野や学生の問いにも非常に率直に答えていたはずで、番組として焦点の絞り込み、鈴木の内面への切り込みが足りず、鈴木の創作史を概観するようなトークに終わった感は否めない。 ワークショップも難しかった。題材として提示されたクリップが非常に抽象的なものだったために、そこから独自のイメージを紡ぐという作業はハードルの高いものであった。鈴木のエクスペリメンタルなサンプリングの試みも含めて、やや消化不良に終わったのではないか。 鈴木慶一といえば、最近では佐野が冨田ラボでボーカルを務めた「ペドロ 〜消防士と潜水夫〜」でも作詞を担当しているが、この作品ひとつ取っても抽象的でありながら独自の喚起力を持った言葉の選び方は顕著だ。そうした点を鈴木の内なる論理性との関係で解き明かして欲しかった。 2010 Silverboy & Co. e-Mail address : silverboy@silverboy.com |