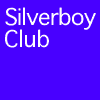 君たちはどう生きるか 君たちはどう生きるか宮崎駿監督の新作「君たちはどう生きるか」を見た。僕は今まで宮崎監督作品を含むいわゆるジブリ作品を劇場はおろかDVDなどでも見たことはなく、テレビで放映があれば片手間に見る程度だったが、今回はたまたま外出の空き時間にちょうど都合がよかったので、初めてカネを払って宮崎作品を見ることにしたのであった。 映画評がまとめられているサイトなどを見ると、この映画の評価がきれいにふたつにわかれているのが興味深い。「すばらしい」「感動した」などのポジティブな評価の一方で、「わからない」「理解できない」といったネガティブな評価も少なからずあり、両者が拮抗している印象を受ける。この「受け取られ方」の偏りはこの映画を見てみようと思った理由のひとつだった。 結論からいえば僕にはこの映画は楽しめたし、胸のどこかを動かされもした。リアリティとファンタジー、そしてその境目、表象するものとされるもの、論理とその破綻、説明できるものと説明できないもの、そうしたものをガバっと包含しながらひとかたまりの「表現」として2時間という時間を転がって行く、それはまさに「物語」と呼ぶにふさわしいものだった。 もちろんそこには見終わっても「わからない」「理解できない」点もあった。「あれはなんだったのだろう」「あれはどういうことだったのだろう」という解決しなかったナゾや疑問も(たくさん)あった。そういう意味では僕もまた「わからない」「理解できない」者のひとりであった。 しかしそれにもかかわらずそこには豊穣なイメージの世界、終わることのない物語の力があり、あがったりさがったり、身を乗りだしたり退屈したり、笑ったりドキドキしたり、うなずいたり首をかしげたり、2時間の作品のなかにはっきりとした起伏があり、それが巧みに構築されていて、しかもその質が高かった。たくさんの疑問を残しながらもそこには「映画を見る」という確かな営為、体験があった。 そこにおいて「わかる」「理解できる」ということは、映画を見るという体験を構成するひとつの要素にすぎない。ミステリーのように映画の最後にはトリックが明かされ、犯人が示され、犯人は逮捕されて事件は解決する、過去の経緯は説明され、伏線は回収され、悪は懲らしめられて懸念はすべて円満に払拭される、そういう映画ではこれはない。 なにがなにを象徴しているのか、どのエピソードはどのシーンと関係しているのか、なぜこの物語世界はこのようであるのか、もちろん「そうか!!」と膝を打つシーンもたくさんあるが、一方で「今のはなんだったんだ」「なんでこれがこうなるんだ」的なこんがらがりも少なからずあり、それが気になる人、「解決」や「理解」が得られないと混乱してしまって楽しめない人にとっては「むずかしい」「おもしろくない」映画になってしまったのかもしれない。 この作品に「わからない」ところがしばしばあるのは、僕たちが生きているこの世界そのものが本質的に不合理で、説明のつかないところだからだ。この世界自体がこんがらがっていて、理不尽で、筋のとおらないところだからだ。 そんな世界のなかで、すこしでもよく生きるための手がかりを得ようとして僕たちは本を読んだり映画を見たり音楽を聴いたりするわけであり、せめてその限られた閉じた物語の内側では筋はとおっていてほしいという気持ちはもちろんあってしかるべきものだ。しかし、僕たち自身もまたそのようにいりくんでこんがらがった世界の構成要素である以上、そこにリアリティを求めれば求めるほど、物語もまたいりくんでこんがらがったものになって行かざるを得ないのはしかたのないことである。 宮崎作品を倍速で見る人は少ないと思うが、「この映画はこれこれこういった映画である」という「情報」だけがほしい人にとっては、この映画はタイパの悪い、要約やまとめのしにくい、消費することのむずかしい作品である。そこでは時間軸は混乱し、善悪は自在に入れ替わり、いとしさと憎しみが同じ場所にある。 ひとつだけ例を挙げるなら、真人がナツコを産屋から連れ戻そうとしたとき、ナツコがそれを拒んで「あんたなんか大嫌い!!」と叫ぶシーンがある。真人はナツコの激しい拒絶に一瞬ひるみながら、それでもなんとかナツコを連れ帰ろうとするし、ナツコが真人を帰そうとするのは彼の身をおもんぱかってのこととも解釈できる。しかし継母と継子という微妙な関係のなかで互いの存在を拒絶しながら求め合い、赦し合うふたつの魂のあいだの火花の散るような強烈な交信を一瞬で焼きつけるこのシーンの描写は、簡単に「わかる」「理解できる」と「消化」することをためらうほど重層的で多義的でそれでいて人間の心の深いところと直接つながっている(これに先立ってアオサギが真人に「本当はあの人(ナツコ)のこと嫌いなんだろ」とささやくシーンが伏線にもなっている)。 このシーンはかろうじてこうやって言葉で解釈することもできるが、たとえば真人が下の世界で目にした巨石の墓はだれの墓なのかとか、下の世界の禍々しい者たちはなぜみな鳥なのかとか、下の世界はなぜ食いしん坊のインコたちでいっぱいになってしまったのかとか、そもそも落下した大隕石と大叔父さまの契約とはなんなのかとか、そんな(答えが用意されているかどうかも怪しいような)疑問をいちいち気にしていたら物語は動因を失って自転することを止めてしまう。 すぐれた映画であればあるほど、その映画がなにを伝えようとしているのか(そもそもなにかを伝えようとしているのかどうかも含めて)、決められた字数に要約するのは困難だ。ナゾには答えがあり、伏線は回収され、作品には伝えたいメッセージがあるというリニア(線形)な対応関係をア・プリオリに前提する限り、この映画だけでなくおよそ物語というものを理解することはできないだろう。 物語は線形な因果関係を証明するために語られるのではなく、そこには矛盾があり、混乱があり、解決しない疑問があり、堂々めぐりがあり、どっちつかずがあり、そうしたものの総体として、なんだかよくわからないけど圧倒的なものとか、なんだかよくわからないけど激しく動かされるものの存在を指し示すものなのである。なぜなら、我々が生きるこの世界そのものが、あるいは我々という存在そのものが、矛盾や混乱をはらみ、解決しない疑問を抱え、堂々めぐりでどっちつかずなもの、非線形なものに他ならないからである。そうした世界や人間というものの存在をリアルに描こうとすればするほど、作品もまた矛盾や混乱や疑問、堂々めぐりやどっちつかずを抱えこんだものにならざるを得ないのは当然だ。 「わからない」「理解できない」からつまらなかったという感じ方の背景には、映画を見ることを、整理された線形な知識や情報、あるいは道義的な教訓とかなんらかの「正解」の獲得だと考える映画観があるのではないかと思う。映画を見ることでその映画についての「正解」が得られるという考え方は、今の自分はいつわりの(あるいはかりそめの)姿でありどこかにもっとすごい「本当の自分」があると考えていつまでも「自分さがし」を続ける感覚に似たものを感じる。 世界がきれいに整理された理解可能なものであるというのは単なる錯覚であり、僕たちは自分が知っていることの少なさにおののきながら生きるしかない。すべてを知ることはできず、すべてを理解することもできない。なにかを知っている、なにかをわかっていると考えること自体が傲慢であり思いあがりである。「わからない」「理解できない」という感想が散見されることは、この映画が豊かな物語を語っている可能性を示唆している。 (2023.8.4) 2023 Silverboy & Co. e-Mail address : silverboy@silverboy.com |