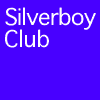 JGB長編レビュー 1988-2000 JGB長編レビュー 1988-2000ここでは88年の「殺す」から最新作の「スーパー・カンヌ」までを取り上げる(但し91年の「女たちのやさしさ」は「太陽の帝国」と合わせて別に論じる予定)。「殺す」から94年の「楽園への疾走」までは6年のインターバルがあり(その間に「女たちのやさしさ」がある訳だが)、「殺す」はむしろ前年の「奇跡の大河」と時期的には近いが、内容的には明らかに「コカイン・ナイト」や「スーパー・カンヌ」と共通点があるため、こちらのグループに入れることにした。 人間の心の奥、あるいはさらにその向こう側に広がる未知の空間に踏み込んで行こうとするバラードの目線はこの時期においてもまったく変わっていないが、この時期の作品の特徴のひとつは作品がリアルな現代社会を舞台にしていることだろう。バラードはもはやその「特殊な」思考を表現するために荒唐無稽な舞台装置を必要としなくなったのかもしれない。「あり得ない」状況の中にゾッとするような真実の瞬間を忍ばせる手法から、当たり前のミステリーの中に目もくらむ現実の裂け目を描く方法論へ。 そう、ミステリー仕立てもこの時期のバラードの特徴のひとつだ。しかし、実際のところバラードは謎解きになどまったく興味はない。それはひとつの「語り」のスタイルという以上の意味は持たないのだ。かつて、彼にとって「SF」がそうだったように。リアルな現代小説、あるいはミステリーの形式を借りながら、彼が繰り返し語りかける物語は少しも変わってなどいないのだから。 2006-2008 Silverboy & Co. e-Mail address : silverboy@silverboy.com |