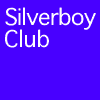 ルー・リード伝 ルー・リード伝
僕が初めて買ったルー・リードのアルバムは1986年の「Mistrial」だった。基本的にカネのない大学生だった僕が、このアルバムをレンタルでもなくわざわざ買ったのは、ひとつには他ならぬ佐野元春が好きなアーティストとしてルー・リードの名前を挙げていたからであり、もうひとつにはルー・リードのアルバムがレンタルになかったからである。 今、あらためて聴けば、ロックの歴史的な流れのなかでの位置づけも、ルー・リードのディスコグラフィのなかでの受け取られ方も理解はできるが、洋楽経験もたいしてなかった20歳そこそこの僕にはこのアルバムはまったくピンとこなかった。某誌のレビューでは「どこか『どん底』感すら漂う」とまで書かれたアルバムである。不運な出会いであった。その3年後に発表されたのが代表作のひとつとされる「NEW YORK」であったことを考えても。 この本を読めば、ルー・リードというアーティストが、もちろん起伏はありつつ、また、それなりのヒットや評価もありつつ、しかし、ピークとか大ブレイクとかいったものとは無縁の、アーティスティックなキャリアを歩んできた人だということがわかる。そこにはまるで理解されることを拒否するような、かたくなでときとして攻撃的ですらあるような固い殻とかとげのようなものを感じる。 だが、彼と親しく交わった人たちの挿話を読めば、実際にはルー・リードはまともな常識人であり、エキセントリックなロック・ミュージシャンとしての「キャラづけ」は多分に意識的で偽悪的、露悪的なものだったのではないかという印象が拭えない。そして、そうしたキャラとしての自分が次第に素の自分を上書きし、彼自身にも自分のホーム・ポジションみたいなものがわからなくなっていたのではないかとすら思うのだ。 おそらく彼自身は性的にはストレートだったと思うが、同性愛が非道徳的とされる社会では、それだからこそ同性愛者的にふるまっていたのではないか。そういうナイーヴさを十代から二十代くらいでうまくしまいこむことができず、いわばこじらせた結果、危うい人生を送りながらも、一方で歴史に残るアルバムを何枚も作ることになったのだ。それはそれでよかったのだろう。ルイス・アラン・リードは自らが作り上げたセルフに殉じたのかもしれない。 もっとも、彼の世代にあっては同性愛的なふるまいだけではなく、ドラッグ・カルチャーやアルコールへの耽溺なども、今日では考えられないくらい強い規範的な抑圧の下で排除される対象だった。それにもかかわらず敢えてワイルド・サイドを歩いたルー・リードの態度は、たとえそれが本質においてナイーヴで偽悪的、露悪的な自己演出に由来するものだったとしても、ロックを含むカウンター・カルチャーが社会に対してその存在を知らしめ、なんらかの居場所を確保するうえで不可欠な役割を果たしたのは間違いない。 カウンター・カルチャーの大物然としたポジションにありながらも、彼が一方で、メインストリームの文学に強い憧憬を抱き続けていたらしいこともわかる。シラキュース大学で詩人デルモア・シュウォーツの薫陶を受け、自分の作品に文学としての価値があることを常に示そうとしていた(そしてそれはかなりうまく行った)。神経の細かいインテリというのがより実像に近いのではないかとは思うが、パブリック・イメージの背後にあるものを、憶測や空想ではなく、丹念な取材の積みかさねて浮かび上がらせた本書にはリアリティがある。 僕がアルバム「Mistrial」以降、彼のアルバムをリアルタイムで聴いていたころには、ルー・リードはもはや危険人物ではなく、かつてはワルもやったが今は落ちついてむしろ格調高いロック詩人としてスゴみを感じさせる存在だった。だから、今回、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドに始まる彼の音楽的キャリアを追体験し、彼がどのように扱われてきたかを知ることができたのはスリリングだった。こういう圧倒的な取材量にもとづくノンフィクションとか評伝みたいなものがしっかり作られ、それを受け入れる文学市場があるのはすごいことだと思う。文化の基礎体力みたいなものが違う。 僕にとってルー・リードはなによりも「声」の人だ。ロック業界には、ボブ・ディラン、ジョン・レノン、エルヴィス・コステロといった、必ずしも「美声」ではなくとも否応なく人の耳を開かせる声を持ったアーティストがおり、ルー・リードもまたその系譜に連なるべき人だと僕は思っている。紙の本から彼の声は聞こえてこないが、その分彼のアルバムを聴き返したくなる労作だ。 (2023.11.18) 2023 Silverboy & Co. e-Mail address : silverboy@silverboy.com |
