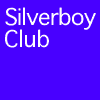 バトル・ロワイアル / 高見広春 バトル・ロワイアル / 高見広春あまりにバカバカしい話だからこそ書けるリアリティみたいなものってある。日本に似たどこかの国の中学生1クラスが、無人島に閉じこめられて最後の一人になるまで殺し合いを強いられるというこの、あまりに荒唐無稽でバカバカしいお話は、しかし、だからこそ僕たちの中の深層心理のようなものを露わにしてしまうのかもしれない。ふだんは何とか隠している人間の強さや弱さが、想像を絶する極限状態の中で顕在化する瞬間をこの小説は描いている。描ききっている、と言ってもいい。 もちろん、こんな中学生離れしたヤツばっかりのクラスなんてあるかよ、とか、結局イノセントな主人公が生き残るんじゃん、とかそういう類のケチならいくらでもつけられる。だが、そんなことはどうだっていいことなのだ。これはもともとあり得ない話なんだから。それよりも物語としての全体性をほとんど放棄しながら細部に宿る圧倒的なリアリティを読め。日常の些細な場面で心の奥深くに起こる静かなさざ波のような感情の揺れがアンプに直結されて大音量に増幅されているのがこの小説だ。 さて、この小説を読むと、壮絶な疑心暗鬼と人間不信の物語が語られた後、それでも最後に愛と友情が勝つのだというテーマが用意されているように思える。例えば本書文庫版の「解説」では、
なんてことになっている。だけど僕はそうは思わない。むしろ書くとするなら、
だろう。金八先生のパロディは単なる悪趣味ではない。それが友情や愛への無批判で無前提な依拠の物語であったからこそ、作者はここでわざわざ武田鉄也を登場させ、あの口調で「今日は、皆さんにちょっと、殺し合いをしてもらいまーす」と言わせる必要があったのだ。ここは眉をひそめる場面ではない。腹を抱えて笑うところだ。僕たちは、あの、楽観的な友情や愛への盲信をいったん笑い飛ばさなければならなかったのだ。 この小説が痛快だとするならそれはこの小説がそのように暑苦しく息苦しい愛や友情を初めっから信用せずにバシバシ殺しまくっているからだろう。このような極限状態の中ではだれもが結局「個」としての自分に返らざるを得ない。自分の生き方を自分で決定しなければならない。ふわふわした信頼や曖昧な信用は結局自分を傷つけるだけだということにだれもが気づいて行くからだ。そして、そのような中で僕たちは必然的に「友情」や「愛」ということの意味を問い直すことになる。この、生きるか死ぬかの情況の中でも有効な友情や愛とは何なのかということを。 答えはもちろんある。それは、たった一人の友達、たった一人のパートナーを守るために40人のクラスメートが死ぬことを受け入れなければならないということだ。本当の愛や友情を貫徹するためにはあなたは自分の手を汚し、それだけのものを冷徹に切り捨てなければならない。そのときあなたの手は血に濡れているだろう。それでもあなたはその「友情」や「愛」を無垢に抱きしめられるのだろうか。あなたは笑うことができるのだろうか。 それはこの本の中だけのできごとじゃない。僕たちの手は現実に血にまみれてる。たとえそれがあなたの目に見えなくても、あなたの手はだれかを押しのけ、だれかを無視し、だれかを傷つけたときの鮮血で真っ赤に染まっているのだ。この小説はそれを少しばかり極端に、分かりやすく語って見せただけに過ぎない。 大切なのは手を汚さないように生きることではないと僕は思う。なぜならそんなことは所詮できっこないから。僕たちがするべきなのはむしろ僕たちの手が血に濡れているということを知ることだ。自分の手にこびりついたクラスメートの血に気づくことだ。 エピローグで街に戻った主人公は、追っ手から逃げながらこう宣言する。
そう、それは続いている。ゲームが終わって街に帰っても。僕の周りでも、あなたの周りでも。 2002 Silverboy & Co. e-Mail address : silverboy@silverboy.com |